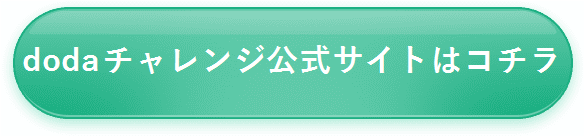dodaチャレンジで断られた!?考えられる理由と該当しやすい人の傾向を詳しく解説


dodaチャレンジに登録したのに断られるって、どうしてなんだろう?自分だけじゃないのかな?
せっかくdodaチャレンジに登録したのに、「ご紹介できる求人がありません」と言われたり、エージェントからやんわりと断られてしまった経験、ありませんか?そんなとき、「なぜ自分だけ…」と落ち込んでしまうのも無理はありません。でも実は、断られる背景にはいくつかの理由があるんです。その原因を知ることで、転職活動の方針を見直したり、新たな方向性を見つけるきっかけにもなります。
この記事では、dodaチャレンジで断られる理由や、そうなりやすい人の特徴、さらに今後どう行動すればいいかといった対処法まで丁寧に解説していきます。この記事を読めば、きっと次の一歩が見えてくるはずです。

dodaチャレンジで断られた場合でも、理由を知って前向きに次の行動を取れば、チャンスは広がります!
断られる理由その1:マッチする求人が見つからないケース
dodaチャレンジでは、求職者の希望と企業側の求人が一致しない場合、「ご紹介できる求人がありません」となることがあります。実際、特定の条件や希望を設定していると、それに合致する求人が極端に限られてしまうのです。特に障がい者雇用の領域では、企業側の環境や条件によって柔軟な働き方が難しい場合もあり、求職者の希望とのギャップが課題となることがあります。

自分の希望が高すぎるだけで、求人が紹介されないこともあるのかな?
希望条件が高すぎる場合(在宅勤務限定・フルフレックス・高年収など)
「在宅勤務しか無理」「年収は最低でも500万円欲しい」「フルフレックスで働きたい」など、条件を絞りすぎると、該当する求人はぐっと少なくなります。特に、障がい者雇用枠は企業側が勤務形態に制約を設けているケースもあり、柔軟な条件設定がカギとなります。
職種や業界のこだわりが強すぎる場合(専門職に限定している)
たとえば、クリエイティブ職やアート系などの専門性が高い分野は、障がい者雇用の中では募集が少ない傾向があります。職種や業界に強いこだわりを持つと、選択肢がかなり限られ、紹介が難しくなる可能性があるのです。
勤務地を限定している場合(地方勤務希望など)
都市部と比べて、地方では障がい者雇用の求人が少ない傾向があります。そのため、勤務地を1つの地域に絞ってしまうと、求人そのものが見つからないという事態になりかねません。勤務地の幅を少し広げるだけでも、可能性が広がることがあります。

条件を少し見直すだけで、紹介される求人の幅が広がることもあるんですね!
断られる理由その2:サポート対象外と判断されるケース
dodaチャレンジは、誰でも無条件に支援を受けられるわけではありません。一定の基準を満たすことで、初めて転職サポートの対象になります。ですので、登録しても状況によっては支援を受けられない場合があるのです。自分の現状が対象に当てはまるかを確認することが、最初のステップになります。

もしかして、自分がサポートの対象外になっているってこともあるのかも…?
障がい者手帳を持っていない場合(原則として手帳が必須)
dodaチャレンジが紹介する求人の多くは、障がい者雇用枠となっています。障がい者手帳の保有が必須であるため、手帳がない場合は求人紹介が難しいのが実情です。手帳の取得が可能であれば、まずはその手続きを検討してみるとよいでしょう。
ブランクが長く、職務経験がほとんどない場合
職歴が乏しく、過去の勤務から長期間離れている場合、企業からの評価が厳しくなることがあります。そのような場合には、職業訓練や短時間勤務からの再スタートを考えると、転職活動が前進しやすくなります。
体調が安定していないと判断された場合(就労移行支援を勧められることも)
エージェントとの面談の中で「まだ働ける状態ではない」と見なされると、まずは就労準備を進める段階と判断されます。その際には、就労移行支援事業所を紹介され、安定した体調づくりから始めることが勧められることがあります。

支援を受けるためには、まずは自分の状況を整えることが大切なんですね!
断られる理由その3:面談時の印象や準備不足が影響してしまうケース
dodaチャレンジでは、登録後に面談を通じて求職者の希望や適性をヒアリングします。その場でしっかりと準備ができていなかったり、伝えるべき情報が曖昧だと、「紹介が難しい」と判断されることもあるのです。面談の準備と自己理解は、転職成功への第一歩といえるでしょう。

面談ってそんなに重要なの?ただの確認だけかと思ってた…
障がい内容や配慮事項を説明できない
自分の障がいの特性や、職場で必要とする配慮を説明できないと、エージェント側もどんな求人がマッチするのか分かりづらくなります。あらかじめ「こんな職場環境だと働きやすい」といった希望を明確にしておくと、適切な提案につながります。
働きたい仕事のビジョンが不明確
「どこでもいいです」「とりあえず働ければいいです」といった曖昧な返答では、エージェント側も求人を絞りきれません。希望職種や業種など、おおまかでもいいので方向性を持っておくことが重要です。
職務経歴をうまく伝えられない
これまでの職務経験をしっかり言語化できないと、適性の判断が難しくなります。自分のキャリアやスキルを簡潔に伝えるために、職務経歴の整理をしておくことをおすすめします。

面談での印象や準備次第で、その後のサポートにも差が出るんですね!
断られる理由その4:地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応のサービスですが、地域によっては求人の数が少ないことがあります。希望エリアや働き方に柔軟さがないと、紹介される求人が見つからないケースが増えるのです。
地方在住(北海道・東北・四国・九州など)
これらの地方エリアでは、障がい者雇用の求人自体が少ないことがあります。都市部に比べて選択肢が限られてしまうため、希望勤務地を柔軟に考えることが重要になります。
完全在宅勤務しか希望していない場合
完全リモート勤務を条件とすると、対応可能な企業が限られてしまいます。リモートにこだわりすぎず、出社日数や距離の妥協点を見つけることで、求人の幅が広がるかもしれません。

働き方に少し柔軟性を持つだけで、求人が見つかる可能性がグッと広がりますね!
断られる理由その5:登録情報に不備や誤りがあるケース
dodaチャレンジに登録する際の情報に不正確な点があると、エージェント側での対応が難しくなるだけでなく、信頼性も損なわれてしまいます。正確な登録情報の入力は、スムーズな転職活動の基本中の基本です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
虚偽の申告をしてしまうと、企業とのマッチング時に大きな問題になります。最悪の場合、内定取り消しのリスクもあるため、必ず正しい情報を入力するようにしましょう。
まだ働けない状態なのに登録してしまった
体調などの理由でまだ働けない状況にもかかわらず、無理に登録してしまうと、求人とのミスマッチが発生しやすくなります。無理をせず、働ける状態になってから改めて登録を検討しましょう。
職歴や経歴を偽っている場合
実際の職歴と異なる内容を記載してしまうと、企業面接時に矛盾が発生し、信頼を失う原因になります。事実に基づいた情報を記載することが大前提です。

正確な情報を記載することは、信頼関係の第一歩ですね!
断られる理由その6:「企業からの不採用」がdodaチャレンジで断られたと感じてしまう
dodaチャレンジで求人を紹介されたあと、企業側の選考で不採用になると、「dodaチャレンジに断られた」と勘違いされることがあります。でもこれは、あくまで企業の判断であり、dodaチャレンジのサポート自体が終了したわけではありません。
不採用は企業側の基準によるものである
企業はそれぞれ異なる採用基準を設けており、紹介されたからといって必ずしも採用されるとは限りません。複数の企業に応募し、粘り強く挑戦することが成功のカギとなります。

「不採用=サポート終了」ではないので、前向きに継続することが大事ですね!
dodaチャレンジで断られた人のリアルな声とは?体験談と口コミから理由を探ってみた

実際に断られた人って、どんな理由でダメだったの?リアルな声を知りたいな。
dodaチャレンジを利用してみたものの、思うように求人を紹介してもらえなかったという声もあります。ここでは、実際にサービスを利用した人たちの体験談を紹介し、どんな人が断られやすいのか、その傾向を探ってみました。「もしかして自分も…?」と感じた方は、対策のヒントとしてチェックしてみてください。
体験談1:軽作業派遣だけの経験でPCスキルも少なめ。紹介は難しいと言われた
障がい者手帳は持っていたのですが、職歴は軽作業の派遣ばかり。PCもタイピング程度しかできず、資格も何もありませんでした。そのため「ご紹介できる求人がありません」と言われ、少しショックでした。
体験談2:体調面の不安から、まずは就労移行支援を勧められた
「継続して働ける状態ではない」と判断され、まずは体調を整えてから、ということで就労移行支援の提案を受けました。焦らずステップを踏むことが大事だと感じました。
体験談3:10年以上のブランクがあり、職業訓練を優先するよう言われた
精神疾患で長期療養していたこともあり、ブランクが10年以上。dodaチャレンジでは、「まずは職業訓練や体調の安定が必要」と言われ、すぐに紹介は受けられませんでした。
体験談4:地方在住+在宅クリエイティブ希望でミスマッチ
四国の田舎町に住んでおり、在宅でのライターやデザイン職を希望しましたが、「ご希望に沿う求人のご紹介はできません」と言われました。やはり地域と職種の掛け合わせは厳しいようです。
体験談5:正社員経験ゼロで、紹介が難しいと言われた
アルバイトや短期派遣の経験はありましたが、正社員として働いたことはありませんでした。そのため、「正社員求人のご紹介は現時点では難しい」と言われてしまいました。
体験談6:子育て中の厳しい条件がハードルに
完全在宅・週3勤務・時短勤務・事務職・年収300万以上という条件を提示したところ、「すべてを満たす求人の紹介は現状難しい」と断られました。条件の見直しが必要だと感じました。
体験談7:障がい者手帳が未取得で登録NG
うつ病の診断は受けていましたが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。そのため、「手帳がないと求人紹介は難しい」と登録時点で断られてしまいました。
体験談8:未経験でITエンジニア職を希望。紹介はされなかった
長年軽作業をしてきましたが、体調を考えて在宅でのITエンジニア職に挑戦したいと思い相談。しかし「未経験からのエンジニア職はご紹介が難しい」とのことでした。
体験談9:通勤困難+短時間勤務希望で該当求人なし
身体障がいがあり通勤が難しいため、在宅で短時間勤務を希望しましたが、「現在ご紹介できる求人がありません」と断られました。
体験談10:管理職&高年収希望で該当求人がなし
以前は中堅企業で一般職でしたが、障がい者雇用で管理職&年収600万以上を希望したところ、「ご紹介可能な求人は現在ありません」との返答を受けました。

体験談からも分かる通り、条件や準備状況によって結果が大きく変わるようです。自分の希望を見直すヒントになりますね!
dodaチャレンジで断られた…そんなときに取るべき具体的な行動とは?

dodaチャレンジに断られたら、もう他の手段もダメなのかな?どうすれば次につながるんだろう?
もしdodaチャレンジで断られてしまっても、そこで転職活動が終わるわけではありません。「なぜ断られたのか」を正しく理解し、それに対して必要な行動を取ることで、再チャレンジのチャンスは十分にあります。
特にスキル不足や職歴のブランク、希望条件が厳しいといった理由で断られた場合には、しっかりと対策を取れば次のステップにつなげることができます。以下では、状況ごとに有効な対処法をご紹介します。
- スキルアップのために職業訓練を受ける
- 条件を見直し、柔軟に対応する
- 他の転職エージェントに登録する
- 就労移行支援を活用して体調やスキルを整える
- 障がい者手帳を取得する方向で動く
特に、就労移行支援や公共の職業訓練などは無料で受けられるものも多く、スキルや自信を身につけるチャンスになります。また、dodaチャレンジ以外にも障がい者向けの転職支援サービスは複数あるため、ひとつのサービスにこだわりすぎないことも大切です。
まずは少し視野を広げて、自分に合った方法を探してみてください。「断られた」経験は、むしろ自分の弱点に気づけたチャンスでもあります。

断られても終わりじゃない!対処法を実行すれば、転職の可能性はグッと広がります!
スキルや職歴の不安がある場合の対処法とは?未経験から前向きに動き出す方法
職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がない…そんな状況だと、dodaチャレンジでの求人紹介が難しいこともあります。でも大丈夫。今からでもできる対策を取ることで、未来の可能性は広がります!

スキルが足りないって言われたら、どうすればいいのかな?今からでもできることってある?
ハローワークの職業訓練を活用する(Word・Excel・データ入力など)
ハローワークでは、PCスキルを身につけたい方に向けた無料または低額の職業訓練があります。WordやExcel、データ入力など、事務職に役立つスキルが基礎から学べるので、未経験でも安心してチャレンジできます。受講後は修了証ももらえるため、履歴書にも書ける実績になります。
就労移行支援を利用して実践スキル+メンタルケアも強化
就労移行支援は、働くために必要なスキルを実践形式で学べるだけでなく、ビジネスマナーや面接対策、生活の安定支援まで含まれている支援サービスです。職場体験や就労実習もあり、自信を持って再スタートできる土台が作れます。
資格取得で「できる自分」を証明しよう(MOSや日商簿記3級など)
資格は、スキルを客観的に証明できる最強のアイテムです。特にMOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級は、事務職や経理職を希望する方におすすめ。資格を取ることで、dodaチャレンジから紹介される求人の幅も広がる可能性が高まります。

今の自分に足りないところを補えば、次のチャンスはきっとつかめますよ!
長期ブランクでサポート対象外に…そんなときに再チャレンジする方法
数年にわたる離職や療養によって、dodaチャレンジのサポート対象外になってしまうこともあります。ですが、「働ける準備」を整えることで、再びチャンスを掴むことは可能です。「まずは少しずつ」が大切なキーワードになります。

ブランクが長いとやっぱり厳しいのかな…でも何か準備できることってあるの?
就労移行支援を活用して「働く習慣」を作る
長いブランクがあると、まずは生活リズムの再構築が重要です。就労移行支援では毎日決まった時間に通所することで生活のペースが整い、企業実習なども経験できるため、働く準備として最適なステップになります。
週1〜2の短時間勤務や在宅ワークから始めてみる
フルタイム勤務はハードルが高くても、短時間のアルバイトや在宅業務なら始めやすいです。週に数回の仕事を継続することで、「安定して働ける状態」であることを証明でき、dodaチャレンジ再登録時にも強みとなります。
企業実習・トライアル雇用制度を活用して実績を作る
ハローワークや就労支援を通じて、トライアル雇用や企業実習に参加するのもおすすめです。実際の仕事に関わることで「ブランクがあるけど、しっかり働ける」という信頼につながりますし、再チャレンジ時のアピール材料になります。

ブランクがあっても、「今できること」を積み重ねることで、次につながる道はしっかり開けます!
地方に住んでいて求人が見つからない…そんなときに試すべき3つの対策
都市部と比べて、地方では障がい者雇用の求人が少ないという現実があります。さらに、フルリモート勤務を希望している場合は、求人そのものが非常に限定されるため、dodaチャレンジでも紹介できる案件がないというケースが起こりやすくなります。そこで今回は、地方在住でも可能性を広げる対処法を紹介します。

田舎に住んでると求人がなくて困る…。フルリモートなら働けるけど、それも難しいのかな?
在宅勤務に強いエージェントも活用してみる
dodaチャレンジだけでなく、在宅勤務に特化した転職エージェントも積極的に利用してみましょう。たとえば「atGP在宅ワーク」「サーナ」「ミラトレ」などは、リモート求人を多く扱っており、自宅から働けるチャンスを広げてくれます。複数のサービスを併用することで、自分に合った働き方が見つかりやすくなります。
クラウドソーシングで経験を積む
自宅でできるお仕事の入口としておすすめなのが、ランサーズやクラウドワークスといったクラウドソーシングサービス。ライティングやデータ入力など、未経験でも始めやすい案件が多く、ここで継続的に実績を積めば、「在宅で働ける人材」としてアピールする材料になります。
地元のハローワークや支援機関で求人を探す
地域密着の求人は、全国対応のエージェントでは見つからないことがあります。ハローワークや障がい者就労支援センターに相談することで、地元企業の求人情報を得られることがあります。地方に根ざした企業は、Webに求人を出していないケースも多く、こうしたルートを通じて掘り出し案件に出会えることも。

地方でも工夫次第で選択肢は広がる!リモートや地元密着の求人ルートを使い分けるのがポイントです!
条件を詰め込みすぎて断られた…?希望を叶えるために見直すべき3つのポイント
「完全在宅」「週3勤務」「年収〇〇万円以上」など、希望条件を細かく設定しすぎると、dodaチャレンジで紹介可能な求人がなくなってしまうことがあります。ですが、その条件を少しだけ見直すことで、転職のチャンスがグッと広がるかもしれません!

条件が多すぎると求人が紹介されないって本当?でも、どこを見直せばいいのか分からない…
まずは「優先順位」をつけて条件を整理しよう
すべての条件を満たす求人は、現実的にはとても少ないです。そこで、「これは絶対に譲れない」「これはできれば叶えたい」といった希望条件の優先順位をつけることで、紹介される求人の幅が広がります。たとえば、「完全在宅が理想」でも、「週1〜2回なら出社可能」と伝えれば、対象求人が増えることがあります。
譲歩できる条件をアドバイザーに再提示しよう
「紹介できる求人がない」と言われた後でも、条件を少し緩めて再度相談すれば、再びサポートを受けられる可能性があります。勤務時間や出社頻度、勤務地などについて、「多少なら調整できる」と伝えるだけで、紹介対象になることがあります。柔軟な姿勢が転職成功へのカギです。
段階的に理想の働き方に近づくステップ戦略を考える
最初から理想通りの条件で働くのが難しい場合は、まずは現実的な条件で就職し、その後スキルを磨きながら希望に近づけていくという方法もあります。たとえば「時短勤務から始めて、将来的にフルタイムへ移行」「最初は一般事務で、経験を積んで専門職にステップアップ」など、長期的な視点でキャリアを築くことが大切です。

条件を少し見直すだけで、チャンスは確実に広がります!まずは「できること」から始めてみましょう!
手帳がない・区分が合わない…そんなときにどう動く?就職の可能性を広げる方法
dodaチャレンジは障がい者雇用枠の求人紹介が中心のため、障がい者手帳を持っていない場合や、支援区分が対象外とされる場合、求人の紹介が難しくなることがあります。でも、だからといって就職の道が閉ざされたわけではありません!ここでは、手帳がない方や区分の問題で断られてしまった方でもできる対策をご紹介します。

手帳がないと求人を紹介してもらえないって言われたけど、何か方法はあるのかな…?
主治医・自治体に手帳の取得を相談してみる
精神障がいや発達障がいなど、見えにくい障がいでも、一定の条件を満たしていれば手帳の取得は可能です。まずは主治医に相談し、診断書の内容や診療実績などをもとに、自治体の窓口で手続きについて確認してみましょう。手帳を取得することで、障がい者雇用枠の求人にチャレンジできるようになります。
手帳なしOKの求人を探す+就労移行支援で準備を進める
ハローワークなどでは、「手帳がなくても応募できる求人」もあります。また、就労移行支援を利用して、スキルや職歴を積んでおくと、後に手帳取得して再登録する際に紹介されやすくなります。今すぐは無理でも、段階的に準備を進めることで、未来の選択肢が広がります。
体調の安定を最優先に。治療後に再挑戦する選択も
体調が不安定な状態では、無理に就職を進めるのではなく、まずは治療に専念するのがベストな選択です。医師と相談しながら、体調が整ったタイミングで手帳を取得し、再びdodaチャレンジに登録することで、よりよい条件での就職が目指せます。

今はできることから始めて、少しずつ準備を整えていけば、就職の道は必ず見えてきます!
その他の対処法:dodaチャレンジ以外の選択肢も活用しよう
dodaチャレンジだけが転職活動の道ではありません。自分に合うサービスを見つけることができれば、他の支援機関でも十分に就職を目指せます。
障がい者向け転職サービスを複数利用する
たとえば、atGP・サーナ・ラルゴ高田馬場などのエージェントは、それぞれに特徴があります。得意な求人分野やサポート体制も異なるため、複数を併用することで、自分に合った求人に出会えるチャンスが広がります。
地域の支援センターやハローワークを活用する
障がい者就労支援センターやハローワークでは、地域密着型の求人情報を扱っています。特に地方の場合、こうした機関のほうが地元企業とのつながりが強く、掘り出し求人が見つかることもあります。
選択肢を広げることが成功への第一歩
転職活動では、「この方法しかない」と決めつけないことが大切です。いろいろな方法を試しながら、自分に合った働き方を模索することで、少しずつ理想のキャリアに近づくことができます。

dodaチャレンジだけじゃない!他のサービスや支援も活用して、自分に合った道を探していきましょう!
dodaチャレンジで断られた…?精神障害・発達障害だと紹介が難しいって本当?

精神障害や発達障害があると、やっぱり就職は難しいのかな?dodaチャレンジで断られたらどうすればいい?
dodaチャレンジを利用しようと思っていたのに、「紹介できる求人がありません」と言われてしまった…そんな経験をした方もいるかもしれません。特に精神障害や発達障害をお持ちの方は、「自分の障害特性のせいで難しいのでは?」と不安になることも多いでしょう。
実際、dodaチャレンジでは障がいの種類や等級、そして求職者の希望条件によっては、紹介が難しくなることもあります。ただし、それは「就職が不可能」という意味ではありません。むしろ、自分に合った対策や選択肢を知ることで、前に進む道が見えてくるはずです。
この記事では、身体障害者手帳を持っている方の就職事情と比較しながら、精神障害や発達障害の場合にどう向き合えばよいかを丁寧に解説していきます。「dodaチャレンジで断られてしまった…」という方でも、次のステップが見つかるヒントになるでしょう。

障がいの特性を理解し、適切な方法で対処すれば、精神・発達障害でも就職は十分に目指せます!
身体障害者手帳を持っている人の就職事情とは?企業側の採用傾向も解説
身体障害者手帳を所持している方は、企業側が配慮しやすいという点から、精神障害や発達障害のある方に比べて、就職のハードルが比較的低いケースがあります。ただし、障がいの程度や内容、通勤の可否によっては求人の選択肢が限られてくることもあるため、自分に合った働き方を見極めることが大切です。

身体障がいのある人は、就職しやすいって聞いたけど…具体的にはどんな違いがあるのかな?
軽度(5~6級)の障がいは幅広い職種で採用されやすい
身体障害者手帳の等級が軽度(例:5級・6級など)の場合、日常生活や業務上の制限が少ないため、オフィスワークや軽作業などの職種に広く応募しやすくなります。企業側も特別な設備や大きな配慮を必要としないため、積極的に採用してくれるケースも多いです。
障がい内容が「見える化」されていることで配慮がしやすい
身体障がいは、外見や診断書などで配慮すべき点が明確になっているため、企業側が受け入れやすいという傾向があります。例えば、車椅子利用者にバリアフリー環境を整備したり、片手の不自由さに合わせてPC操作環境を調整したりと、具体的な配慮がしやすいため、採用へのハードルが下がります。
合理的配慮が具体的に提供しやすいことがメリット
合理的配慮とは、障がい者が働きやすいように企業が提供する支援のこと。身体障がいの場合、配慮の内容が明確なため、たとえば「業務の一部制限」や「オフィスの構造変更」など、企業も対策を取りやすく、採用を検討しやすくなります。
通勤・作業が難しいケースでは選べる求人が減る
上肢や下肢に障がいがある場合、階段しかないオフィスや、身体を動かす業務などは難しくなるため、求人の選択肢はやや限られてしまうことがあります。ただし、在宅勤務や座り仕事中心の職種では比較的マッチしやすく、求人も増加傾向にあります。
コミュニケーション能力が高ければ一般職種も視野に
身体障がいがあっても、対人スキルやコミュニケーション能力に問題がなければ、事務職やカスタマーサポート、営業などの職種でも十分に活躍できます。企業側も、業務遂行に支障がないと判断すれば積極的に採用する傾向があります。
PCを使う事務職は特におすすめ
身体的な負担が少ないPC業務(事務職・データ入力など)は、身体障がい者の中でも人気の高い職種です。求人の数も比較的多く、在宅勤務との相性も良いため、働きやすさと採用されやすさを両立しやすい分野と言えます。

身体障がいがあっても、状況に応じて配慮が受けられる環境なら、十分に就職チャンスはありますね!
精神障がいでは「症状の安定性」と「継続勤務のしやすさ」が最重要ポイント
精神障がいを持つ方の就職では、企業が最も重視するのは安定して働けるかどうかです。過去に長期休職をしていたり、転職回数が多い場合などは、企業側が採用に慎重になるケースもあります。面接前に生活リズムを整えておくことが、信頼獲得の第一歩です。
見えにくい障がいだからこそ、企業は配慮の仕方に不安を抱きやすい
精神障がいは外見から分かりにくく、企業側は「どんなサポートが必要なのか」「仕事に支障が出ないか」といった不安を抱えやすい傾向があります。そのため、どんな環境なら安定して働けるかを自分自身で整理し、応募時や面接で具体的に伝えることが重要です。
面接では「配慮事項の伝え方」がカギになる
面接の場では、自分の障がいの特性を正確に伝えるだけでなく、「このような配慮があれば働けます」と前向きかつ具体的に説明することが求められます。例:「電話応対は苦手なので、主にメール対応にしていただきたい」「通院のため月1回休みが必要です」など。配慮が多すぎると企業が対応できないと判断する場合もあるため、必要最小限の配慮で働ける姿勢をアピールするのも有効です。

自分の特性を「どう伝えるか」が、企業からの信頼につながります!
療育手帳(知的障害者手帳)を持つ方の就職事情とは?A判定とB判定で変わる選択肢
知的障がいがある方が所持する「療育手帳」は、その区分(A判定・B判定)によって、就職の難易度や就労形態が大きく異なります。ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
A判定(重度)の場合は福祉的就労がメインに
重度の知的障がいを意味するA判定の方は、就労継続支援B型などの福祉的就労が主な選択肢になります。B型事業所では、個々のペースに合わせて作業ができるため、無理なくスキルを身につけることができます。
B判定(中軽度)の方は一般就労も視野に
中軽度の知的障がいとされるB判定の方は、企業の障がい者雇用枠での就労も十分に可能です。軽作業や清掃、事務補助など、比較的シンプルな作業が多い職種に応募しやすく、適切なサポートがあれば一般枠での就職も目指せます。

判定の区分によって就労の方向性は変わりますが、自分に合った環境を選べば就職も十分可能です!
障がいの種類によって就職の難しさは変わる?就職のしやすさを一覧で解説
障がい者雇用枠での就職活動においては、障がいの種類ごとに就職の難易度が異なります。
一般的には、「企業側が配慮しやすい」「状況が明確で対応しやすい」障がいの方が、採用されやすい傾向にあります。たとえば、身体障がい(特に軽度)は、必要な配慮がはっきりしており、企業も対応しやすいため、比較的就職がスムーズです。
反対に、精神障害や発達障害は見た目に分かりにくいため、企業が配慮の内容を把握しづらく、慎重になるケースがあります。知的障害の場合は、療育手帳の区分(A判定・B判定)によっても就労先や難易度が変わってきます。
それぞれの特性に合わせた準備と対策を行うことで、就職の可能性は大きく広がります。たとえdodaチャレンジで断られたとしても、他の転職支援サービスや福祉的支援機関を活用しながら、自分に合った道を見つけることが大切です。

自分の障がいの種類って、就職にどのくらい影響するんだろう?どんな職種が向いているのかな?
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 向いている職種 | 難易度のポイント |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で企業対応がしやすい |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定される |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状の安定と職場定着がポイント |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | サポート体制がある職場で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型事業所) | 一般就労は難しく、福祉中心の支援が必要 |

自分の障がいに合った職場環境を選べば、就職の可能性はしっかり広がります!
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いとは?自分に合った働き方を選ぶポイント
障がいのある方が就職活動を進める際に悩むのが、「障害者雇用枠で応募するか」「一般雇用枠で挑戦するか」という選択です。どちらを選ぶかで、働き方や職場での配慮の内容が大きく変わるため、それぞれの特徴をよく理解して、自分に合った方法を見極めることが大切です。

障害者雇用枠と一般雇用枠って、具体的にどう違うの?自分にはどっちが向いてるんだろう…
障害者雇用枠のポイント1:法律に基づいた特別な雇用制度
障害者雇用枠は、企業が法定雇用率に従って設けている枠であり、障がいのある方が働きやすいように配慮や支援を前提とした雇用になります。制度として守られているため、就労前から配慮内容の確認や相談がしやすいのが特徴です。
障害者雇用枠のポイント2:法定雇用率は2024年4月から2.5%に引き上げ
障害者雇用促進法により、企業には従業員の2.5%以上を障がい者として雇用する義務があります(2024年4月〜)。そのため、多くの企業が積極的に障がい者雇用に取り組んでおり、雇用枠の数も年々拡大しています。
障害者雇用枠のポイント3:配慮事項をあらかじめ伝える「オープン就労」
この枠では、障がいの内容や必要な配慮を企業に開示した上で雇用されることが前提となっています。たとえば「週に1回の通院が必要」「音に敏感なため静かな環境で働きたい」など、事前に共有することで、企業側も働きやすい環境を整えてくれます。
一般雇用枠のポイント1:すべての応募者が同じ基準で評価される
一般雇用枠では、障がいの有無を問わず、スキルや経験、実績での選考になります。そのため、配慮を求めることは原則できず、自己管理の能力や業務遂行力が求められます。
一般雇用枠のポイント2:障がいを開示するかは自分次第(オープン or クローズ)
この枠では、障がいを開示(オープン就労)するか非開示(クローズ就労)にするかは自分で選べます。ただし、開示することで一部配慮を受けられる可能性がある一方、非開示の場合は完全に一般と同様の条件で勤務することになります。
一般雇用枠のポイント3:配慮は原則なし。自分で乗り越える必要がある
一般雇用枠では、特別な配慮や支援を受ける前提ではないため、自分の障がいに合わせて働き方を工夫したり、企業文化との相性を見極めたりする力が求められます。自己理解と自己管理が非常に重要になる枠です。

自分に合った働き方を選ぶためにも、それぞれの雇用枠の違いをしっかり理解しておくことが大切ですね!
年代別にみる障がい者の採用傾向とは?年齢によって違う就職の難しさ
障がい者の就職事情は、年代によって大きく異なる傾向があります。特に若年層は就職活動がしやすく、年齢が上がるにつれて求人の選択肢や採用率に変化が出てきます。

年齢が高いと、やっぱり障がい者雇用でも就職が難しくなるのかな…?
厚生労働省の「障害者雇用状況報告(2023年)」をもとに解説
厚生労働省が発表した2023年版の「障害者雇用状況報告」によると、障がい者の雇用率は年々上昇しており、2023年時点では民間企業の雇用率が約2.3%に達しています。さらに2024年4月からは法定雇用率が2.5%に引き上げられる予定で、今後も採用の機会は増えていくと予想されます。
しかし、年齢別に見ると、20代・30代の若年層は未経験OKの求人も多く、比較的採用されやすい一方、40代以降は「経験者採用」が中心となるため、就職のハードルが高くなる傾向があります。特に、軽作業や事務補助といった職種では、若い人材が優遇されやすい現実もあります。
とはいえ、年齢が高くてもスキルや経験次第で十分に就職は可能です。PCスキルを磨いたり、職業訓練を受けて再チャレンジすることで、在宅勤務など柔軟な働き方も選択肢に入ってきます。
| 年代 | 構成比(全体比) | 主な就業傾向 |
|---|---|---|
| 20代 | 約20〜25% | 未経験可の求人が多く、初めての就職に有利 |
| 30代 | 約25〜30% | スキルや経験を活かした転職が中心 |
| 40代 | 約20〜25% | 職歴によって差が大きく、未経験は難しい傾向 |
| 50代 | 約10〜15% | 経験職種での採用が中心。求人数はやや少なめ |
| 60代 | 約5% | 再雇用・短時間勤務・福祉就労などが中心 |

年代に合った戦略をとれば、どの年齢層でも就職のチャンスはあります!自分に合った道を探してみましょう。
dodaチャレンジには年齢制限がある?50代・60代でも使えるのか徹底解説!
障がい者向けの転職サービスを検討している中で、「年齢が高いと断られるのでは?」と不安になる方も多いはず。実際、dodaチャレンジのようなエージェントに公式な年齢制限はありませんが、実質的にターゲット年齢があるという現実も存在します。

50代や60代でもdodaチャレンジって使えるの?年齢が理由で求人を紹介されないこともあるのかな…
公式な年齢制限はなし。ただし実質的には「50代前半まで」が中心
dodaチャレンジでは、明確な年齢制限を設けていないため、誰でも登録・相談は可能です。しかし、実際に紹介される求人の多くは20代〜50代前半をターゲットにしている傾向があります。企業側が「長期的に働ける人材」を求めることが多いため、50代後半~60代になると紹介が難しくなるケースが増えてきます。
ただし、50代以上でも専門スキルや職務経験が活かせる求人や、短時間勤務・在宅勤務など柔軟な働き方を選べる求人も存在するため、完全にチャンスがないわけではありません。
ハローワーク障がい者窓口や職業センターも併用するのが賢い選択
年齢やブランクが理由でdodaチャレンジでの求人紹介が難しかった場合は、ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)の利用もおすすめです。
これらの公的機関では、年齢に関係なく応募できる求人の紹介や、職業訓練・面接指導などの支援を受けることができます。特に、職業センターでは職場実習や職業評価なども行っており、未経験の仕事へのチャレンジを支援してくれる体制が整っています。
就活エージェントと公的支援機関を併用することで、年齢にとらわれず、自分に合った求人を探せる選択肢が大きく広がります。

年齢に関係なく、「自分に合ったサービスを使い分ける」ことが就職成功のカギになります!
dodaチャレンジの評判やサポート内容は?よくある質問から疑問を解決!

dodaチャレンジって実際どうなの?評判や対応が気になるけど、ネットの情報だけじゃ不安…
「dodaチャレンジを利用してみたいけど、断られることがあるって本当?」「サポートの質はどうなの?」といった不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。転職サービスを選ぶ上で、実際の利用者の声やサポート内容を知っておくことはとても大切です。
このセクションでは、dodaチャレンジに関してよく寄せられる質問とその回答を、わかりやすく丁寧に解説していきます。さらに、気になる項目について詳しく知りたい方のために、関連記事のリンクも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

疑問を解消してから利用することで、dodaチャレンジをより有効に活用できますよ!
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの利用者からは、「求人紹介が早くて助かった」「カウンセリングが親身だった」といった好意的な口コミが寄せられる一方、「希望と違う求人ばかりだった」「面談後に連絡が途絶えた」といった声も一部あります。
賛否両方の口コミがあるため、利用前にリアルな声をチェックしておくのがおすすめです。以下の関連ページでは、実際の利用者の評判を詳しく紹介しています。
関連ページ:dodaチャレンジの評判や口コミまとめ!障害者雇用の特徴とメリット・デメリットを解説
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
「紹介できる求人がありません」と断られてしまった場合でも、対応方法はあります。希望条件の見直しやスキルの強化、他のエージェントの併用などによって、再び求人を紹介される可能性が高まります。
たとえば、職業訓練でPCスキルを身につけたり、在宅勤務に対応した求人を扱う他サービスを使うのも効果的です。以下のページでは、断られたときの具体的な対策を解説しています。
関連ページ:dodaチャレンジで断られることがある?難しいと言われる理由や対処法、体験談をチェック!
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
面談後に連絡がない場合、いくつかの理由が考えられます。求人のマッチングが難航している、企業側との調整に時間がかかっている、またはメールの不達や連絡ミスなども可能性としてあります。
数日待っても連絡がない場合は、一度自分からエージェントに確認してみると良いでしょう。詳しい対応方法や事例については、以下のページをご参照ください。
関連ページ:dodaチャレンジから音沙汰なし?面談・求人・内定のケース別に理由と対処法を紹介
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、これまでの職務経験や転職理由、希望の職種・勤務地・働き方などのほか、障がいの内容や必要な配慮について詳しく聞かれます。
面談前に、職歴や希望条件を整理しておくと、スムーズに対応できます。聞かれる内容や面談の流れについて詳しく知りたい方は、以下の関連ページを参考にしてください。
関連ページ:dodaチャレンジ面談で内定を掴む!流れ・注意点・対策・準備のポイントを徹底解説
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者専門の転職支援サービスで、キャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートしてくれます。求人紹介だけでなく、応募書類の添削や面接対策、企業との日程調整まで対応してくれるのが特徴です。
障がいの特性に配慮したマッチングが行われるため、自分に合った職場を見つけやすく、安心して転職活動に取り組めます。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジでは、障がい者雇用枠の求人を主に扱っているため、原則として障がい者手帳の所持が必要です。手帳がない場合は、求人紹介を受けられないことが多いです。
ただし、手帳の取得を検討している段階であれば、アドバイザーが申請に関する情報や今後の流れについてアドバイスしてくれることもあります。詳しくは以下の関連ページをご覧ください。
関連ページ:dodaチャレンジは手帳なしで応募できる?障害者手帳の必須条件や申請中の利用を解説
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類に関係なく登録可能ですが、支援の対象外となるケースもあります。
たとえば、職歴がほとんどない、長期離職中、体調が不安定で継続勤務が難しいと判断された場合は、まず就労移行支援を案内されることがあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、担当のキャリアアドバイザーに直接連絡するか、公式サイトの問い合わせフォームから申請することで手続きが可能です。
転職活動に支障が出ないよう、退会前に確認事項を整理しておくと安心です。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、主にオンライン(電話やWeb)で行われます。
地域によっては対面での面談も可能なので、希望がある場合は事前に問い合わせて確認してみましょう。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
公式には年齢制限は設けられていませんが、実際には50代前半までが中心の対象層とされています。
50代後半以降の方は、ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センターも併用することで、より多くの求人に出会える可能性が広がります。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、dodaチャレンジは離職中の方でも登録・利用が可能です。
ただし、ブランクが長い場合や直近の職歴がない場合は、紹介可能な求人が限られることもあるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは主に転職を希望する方向けのサービスです。
学生や新卒の方の場合は、大学のキャリアセンターや新卒向けの障がい者就職支援サービスを併用するのが現実的です。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られることも?他の障がい者向け就職支援サービスとの違いを比較解説!

dodaチャレンジって、どんなサポートをしてくれるの?他のサービスとどう違うのか気になります…
「dodaチャレンジを利用してみたいけど、求人を紹介してもらえなかったらどうしよう?」「他の就職支援サービスとの違いは?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、dodaチャレンジでは、求職者の条件や状況によって求人の紹介を断られるケースもあります。しかしこれは、dodaチャレンジに限った話ではなく、他の障がい者向け転職サービスでも共通して見られる傾向です。
重要なのは、各サービスの特徴や支援内容をしっかりと理解し、自分に合った選択をすること。そこでこのセクションでは、dodaチャレンジのサポート体制や強みを他の障がい者就職サービスと比較しながら、失敗しないサービス選びのポイントを詳しく解説していきます。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
|---|---|---|---|
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー (atGP) |
1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビ パートナーズ紹介 |
350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援 ミラトレ |
非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッド チャレンジ |
260 | 東京、神奈川、 千葉、埼玉、大阪 |
全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、 東海、福岡 |
全ての障害 |

サービスごとの特徴を知ることで、より自分に合ったサポートを受けることができます!
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ

結局、どうすればdodaチャレンジで紹介を断られずに済むの?他の選択肢も気になる…
dodaチャレンジは障がい者向けの転職支援サービスとして信頼されていますが、「紹介できる求人がない」「ご希望に合う求人はありません」といった形で断られてしまうケースもあります。断られる原因として多いのは、希望条件が厳しすぎる、障がい者手帳の未取得、体調が不安定で就労が難しい、地方在住で求人が少ない、あるいは職務経歴やスキルが不足していることなどです。実際に断られた方の体験談からも、これらの背景が浮かび上がっています。
ただし、これはdodaチャレンジに限った話ではなく、他の障がい者向け就職エージェントでも同様のことが起こり得ます。大切なのは、現状を正しく理解し、スキルや条件を見直すこと。就労移行支援を活用したり、dodaチャレンジのFAQをチェックすることもおすすめです。また、dodaチャレンジの評判や、断られたときの対処法などもあわせて確認しておくと、今後の行動が取りやすくなります。
「dodaチャレンジでダメだったから転職は無理」と思い込まず、自分に合った働き方や支援機関を柔軟に探す姿勢が大切です。行動を止めないことが、次のチャンスを引き寄せます。焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。