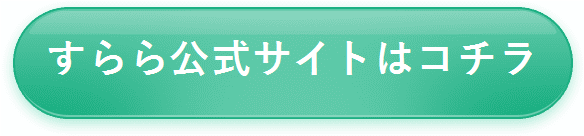すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
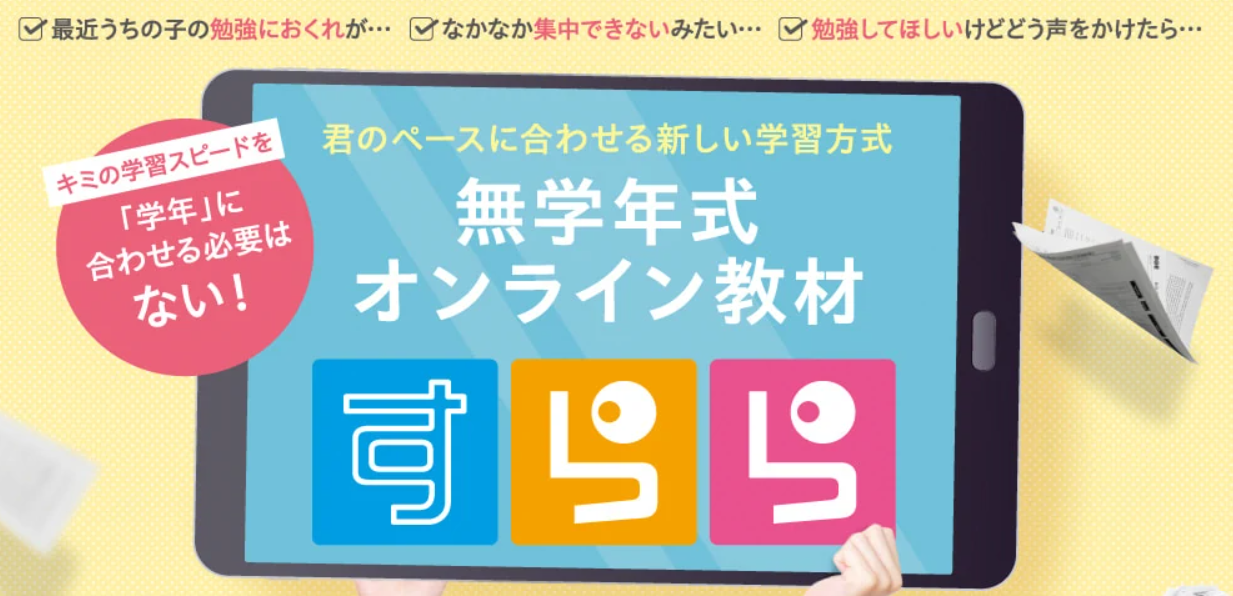

すららって、どうして不登校でも出席扱いとして認められるの?その理由が知りたい!
すららは、不登校の子どもでも出席扱いを目指せる教材として、注目を集めています。文部科学省が推進する「ICTを活用した出席扱い制度」に基づき、一定の条件を満たすことで、学校の出席日数として認められることがあるのです。
本記事では、「すらら」がなぜ出席扱いになりやすいのか、その具体的な理由や成功のためのポイントを詳しく紹介していきます。
理由1・学習の質と記録が客観的に証明できるから
すららでは、学習内容と進捗を自動で記録するシステムが導入されており、「どのくらい、何を、どのように学んでいるか」をデータとして可視化できます。
学校に提出できる学習レポートが用意されている
すららには、学校提出用の学習レポート機能があります。これにより、家庭での学習状況を客観的なデータとして示すことが可能で、学校側の信頼を得やすくなります。
保護者の負担が少なく、学習管理もスムーズ
学習記録は自動的に保存されるため、保護者が一から管理する手間が不要です。学校側にも明確な記録として提出でき、出席扱いの認定に向けた大きなアドバンテージになります。
理由2・個別最適な学習計画と継続サポートがあるから
すららは、単なる教材ではなく学習支援体制が充実しているのも特徴です。自分のペースで学べる無学年式システムと、すららコーチによる個別サポートが組み合わさっています。
学習の「計画性」と「継続性」をセットで支援
すららコーチが、お子様の理解度や生活リズムに合わせた学習計画を一緒に考え、日々の取り組みを見守ってくれます。これにより、学校側に対しても「学習の継続」が説得力を持ってアピールできます。
進捗の管理までコーチがサポート
コーチは、保護者と連携しながら、子どもの状況に合わせて計画を調整してくれます。学びの抜けや偏りも防ぎ、出席扱いに必要な「計画的・安定的な学習の証明」につながります。
無学年式だから、学年を問わず柔軟に対応できる
すららは「無学年式」教材なので、苦手な単元はさかのぼって復習でき、得意な分野は先取り学習が可能です。復学後の授業にもスムーズに適応できるようになります。

すららは、記録・計画・継続の3つが揃っているから、出席扱いの申請でも安心して活用できるね!
理由3・家庭・学校・すららの三者がしっかり連携できるから
すららは「家庭・学校・教材」の三方向での連携が取りやすい構造になっており、出席扱いをスムーズに進めるためのサポートが非常に充実しています。
必要書類の準備方法もサポートしてくれる
出席扱いを申請する際には、学習記録や申請書などの書類提出が必須です。すららでは、必要な書類の種類や準備方法を丁寧に案内してくれるので、初めての手続きでも迷うことなく進められます。
専任コーチがレポート提出をフォロー
すららの専任コーチが学習記録のフォーマットを提供し、提出のタイミングや内容についてもサポートしてくれます。このフォローにより、学校に適切な情報を伝えることができ、出席扱いの認定が進みやすくなります。
担任・校長との連携サポートも万全
学校とのやり取りが不安な場合でも、すららは担任や校長とスムーズに連絡が取れるようフォローしてくれます。これにより、家庭だけでなく学校側との協力体制が築きやすくなり、安心して申請を進めることが可能です。
理由4・文部科学省が認めた「不登校支援教材」として実績がある
教育委員会や学校との導入実績が多数
すららは全国の自治体や教育委員会との協働で導入されており、信頼性の高い学習ツールとして多くの学校現場で採用されています。
その結果、不登校の子どもが「学校と同様の環境で学習できる」教材として高く評価されており、実際にすららを使って出席扱いを受けたケースも数多くあります。
公式に「不登校対応教材」として認められている
すららは、文部科学省が推奨する不登校児童生徒支援のための教材として、公式に利用されている実績を持っています。これにより、学校側も出席扱いの判断をしやすくなる点が大きな強みです。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
学習指導要領に準拠した教材だから安心
すららの学習カリキュラムは、文部科学省の学習指導要領に準拠して作られており、学校の授業と同じ学びが家庭でできるよう設計されています。
このため、学校の授業に参加できない状況でも、遅れを感じずに学習を進めることができるのが魅力です。
進捗や理解度を可視化し、フィードバックも充実
すららは、学習の進捗や理解度をシステムで管理でき、テスト機能や復習支援も完備されています。
これにより、学校側が「適切な学習が行われている」と判断しやすくなり、出席扱いの認定がスムーズになる傾向があります。

すららは、教材としての実力はもちろん、申請支援や信頼性の面でも優れてるから、出席扱いを目指す家庭にはぴったりだね!
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

すららを使って出席扱いにしてもらうには、どんな手続きが必要なの?具体的な申請の流れを知っておきたい!
すららを活用すれば、不登校のお子さんでも学校での出席扱いを目指すことができます。ただし、出席扱い制度を適用するには、学校や教育委員会への申請が必要です。
申請の流れは地域や学校によって多少異なるものの、基本的な手順を押さえておけばスムーズに対応できます。ここでは、すららを使って出席扱いを目指すための申請手順を、分かりやすく解説します。
申請方法1・まずは担任や学校に相談する
最初にすべきことは、学校の担任・学年主任・校長先生へ相談することです。学校ごとに出席扱いへの対応方針が異なるため、なるべく早めに動くことがポイントになります。
必要書類や条件を学校側と事前に確認する
出席扱いの申請には、すららの学習記録、学校指定の申請書、場合によっては医師の診断書などが必要です。必要書類の種類やフォーマット、提出先など、細かい点は学校ごとに異なるため、確認と準備がとても重要です。
申請方法2・医師の診断書を用意(必要な場合)
すべてのケースで必要なわけではありませんが、不登校の原因が体調不良や精神的な理由にある場合は、医師の診断書が求められることがあります。
診断書が求められるケースも多い
特に精神的な不調が理由の場合は、医師の意見書が出席扱いの判断材料となります。事前に学校から求められる書類の詳細を確認しておくと安心です。
「不登校であること」と「学習継続が望ましいこと」の記載を依頼
診断書を依頼する際は、精神科・心療内科・小児科などの医師に、不登校の状態と学習への意欲についても記載してもらえるようにお願いしましょう。より前向きな内容があることで、学校側も出席扱いを認めやすくなります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでの学習内容は、出席扱いの申請時に非常に重要なエビデンスとなります。日々の学習進捗をしっかりと記録し、必要書類として提出しましょう。
学習レポートをダウンロードして学校に提出
すららには、学習の進捗状況をまとめたレポート機能があります。このレポートを担任や校長先生に提出することで、家庭でも継続的な学習が行われていることを示すことができます。
申請書の作成は学校、保護者はサポート
出席扱い申請書の作成は、基本的に学校が行いますが、保護者からの学習報告や説明が求められることも多いです。学校との連携を取りながら、しっかりサポートしましょう。
申請方法4・最終的には学校や教育委員会の承認が必要
書類の準備が整ったら、学校での確認・承認手続きに進みます。
最終判断は学校長の承認
出席扱いの認定は校長先生の判断によって決まります。必要書類をしっかり揃えて、説得力のある申請を行うことが成功のカギとなります。
教育委員会への申請が必要なケースも
地域によっては、教育委員会の承認も必要になる場合があります。学校側と連携しながら、必要書類の準備や手続きをスムーズに進めていきましょう。

出席扱いにするには、段階を踏んで申請するのが大事!すららなら学習記録もフォーマット付きで安心だね!
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

すららを使って出席扱いになると、どんなメリットがあるの?内申点や将来にも関係するのかな?
すららを通じて出席扱いを受けることができれば、不登校の影響を最小限に抑えながら、子どもが自信を持って学習を続けられる環境を整えることができます。
内申点や進学への影響、学習の遅れへの不安、そして精神的なプレッシャーなど、不登校によって生じるさまざまな問題をカバーできるのが、すららを活用する大きなメリットです。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
学校の成績評価において、出席日数は非常に大きな要素となります。すららで出席扱いを受けることで、長期欠席による内申点の低下を防ぐことができます。
出席扱いによって出席日数がカウントされる
中学校や高校では、出席状況が成績や内申点に直結しますが、すららを活用して継続的な学習を証明すれば、欠席日数ではなく出席扱いとして反映されます。これにより評価のマイナスを防ぐことができます。
進学への選択肢を狭めずに済む
高校受験や大学進学において、内申点は重要な評価項目です。出席扱いになることで、不登校による不利な条件を減らし、選択肢を広げることができます。
メリット2・「遅れている」という不安が解消しやすい
不登校が続くと、勉強の遅れに対する不安や、「取り戻せないのでは?」という焦りを感じやすくなります。すららを使えば、自分のペースで着実に学習を継続できるので、こうした不安をやわらげることが可能です。
無学年式で遅れを取り戻せるカリキュラム
すららは無学年式を採用しており、学年の枠にとらわれずに、理解できていない部分をさかのぼって復習することができます。また、得意な分野は先に進めることもでき、効率よく遅れをカバーできます。
学習の継続が子どもの自己肯定感を高める
勉強ができていないという劣等感は、自己肯定感の低下を招きやすいですが、すららを使って「今日も学習できた」と実感を積み重ねることで、前向きな気持ちで学びを続けられるようになります。

出席扱いになるだけでなく、すららを使って学び続けることで子ども自身の「自信」も育てられるのがいいところだね!
メリット3・保護者の精神的な負担が軽減される
子どもが不登校になると、「学習が遅れてしまうのでは」「将来どうなるのか」と、保護者の不安も大きくなります。しかし、すららで出席扱いが認められることにより、保護者の心にも余裕が生まれ、落ち着いて子どもを見守ることができるようになります。
すららコーチと学校との連携で、保護者が一人で悩まなくていい
すららには「すららコーチ」という学習支援スタッフがついており、学習計画の作成から進捗管理までをフォロー。さらに、学校・家庭・コーチの三者が連携して情報共有を行うことで、保護者がすべてを抱え込まなくても済む体制が整っています。
「どう支えたらいいかわからない」と悩む前に、専門スタッフの力を借りながら共に子どもを支えていける環境があることが、すららの大きな魅力です。
メリット4・文部科学省が認めた教材だから学校の信頼度が高い
教育委員会や学校との導入実績が豊富
すららは全国の教育機関と連携し、不登校の子どもたちの学習支援を行ってきた実績があります。多くの教育委員会や学校で採用されていることで、その信頼性は非常に高く、出席扱い申請時にも強力な材料となります。
「不登校支援教材」として公式に活用されている
すららは文部科学省のガイドラインに沿った不登校支援教材として、多くの公的機関でも採用されています。これにより、学校側も「すららなら出席扱いが妥当」と判断しやすくなる点がメリットです。
メリット5・「学校に準ずる学習環境」として認められやすい
学習指導要領に沿ったカリキュラムで安心
すららの教材は、文部科学省の学習指導要領に準拠しており、学校で学ぶ内容と同じ単元をカバーしています。学校に通っていない期間も、学習内容にズレが出ることなく継続できるのが大きな利点です。
学習の評価とフィードバックもシステムで可視化
すららは、学習の進捗や理解度をシステムで把握できる仕組みを持っており、テスト・レポート・復習の流れが自動で記録されます。これにより、学校側が「学習がきちんと行われている」と判断しやすくなり、出席扱いとしての承認も得やすくなります。

すららは、子どもだけじゃなく親や学校にも配慮された設計だから、出席扱いの成功率が高いんだね!
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららで出席扱いにするためには、どんなことに気をつければいいの?失敗しないためのポイントを知りたい!
すららを使って出席扱いの申請を成功させるには、学校や教育委員会との信頼関係や、適切な準備が不可欠です。
制度をうまく活用するには事前確認と丁寧な説明がカギとなります。ここでは、申請時に押さえておきたい注意点を具体的に紹介していきます。
注意点1・学校側の理解と協力が必須条件
どれほど自宅でしっかり学習していても、学校側の理解と協力がなければ出席扱いにはなりません。まずは学校が制度や教材を正しく理解していることが重要です。
「すらら=文部科学省ガイドラインに準拠している教材」であると伝える
すららは、文科省の「ICTを活用した出席扱い制度」に準拠した教材ですが、この事実を知らない先生も少なくありません。申請の際には、公式なガイドラインに沿っていることを丁寧に説明し、学校に理解を促しましょう。
資料を持参し、担任だけでなく校長や教頭にも説明を
出席扱いの最終判断は校長が行うことが多いため、担任だけでなく、教頭先生や校長先生にも早めに説明することが大切です。すららの概要がわかる資料なども活用して、制度の信頼性をきちんと伝えるようにしましょう。
注意点2・医師の診断書や意見書が求められるケースがある
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書の提出が出席扱いの条件となることがあります。特に精神的な理由や身体的な健康問題が関係している場合は要注意です。
精神的な理由・体調不良が原因なら診断書が必須になることも
学校や自治体によっては、医師の意見が出席扱いの判断材料として重要視されます。心療内科・精神科・小児科など、状況に応じた医療機関に相談しましょう。
診断書の取得は「出席扱いのため」と明確に伝える
医師に相談する際は、「すららを使って家庭学習を継続していること」や「出席扱いを申請するために必要」であることを具体的に伝えると、より適切な内容で記載してもらえる可能性が高くなります。
家庭学習の様子・学習意欲を医師にも伝えておく
診断書の内容には、単に「不登校状態」とだけ書かれるのではなく、「家庭学習を続けている」「学ぶ意欲がある」といった前向きな記載があると、学校側に良い印象を与えやすくなります。

学校と医師、どちらにも「信頼してもらう説明」が必要なんだね!すららの資料や学習実績を活かすのがポイントだ!
注意点3・学習時間と内容が学校水準に近いことが求められる
出席扱いを認めてもらうには、学習内容と時間が「学校に準ずる」ことが重要です。単なる自習や短時間の学習では、基準を満たさない可能性があります。
「自習感覚」ではなく、「学校と同じレベルの内容」で学ぶ
すららを使う際は、国語・算数・英語・理科・社会といったカリキュラム全体をバランスよく進めることが求められます。好きな教科だけの学習ではなく、文部科学省の学習指導要領に沿った学習が行われているかを意識しましょう。
学習時間の目安は「1日2〜3時間程度」
出席扱いの判断基準には、学習にかける時間も含まれます。短時間の勉強だけでは認められにくいため、継続的に2〜3時間の学習を目指すと効果的です。
主要教科以外も含めて、教科バランスを重視
理科や社会など、主要5教科すべてに取り組むことが望ましいとされます。偏りなく学習を進めていくことで、学校側の理解を得やすくなるため注意しましょう。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが不可欠
学習状況を学校と共有することが出席扱いの条件になることも
出席扱いを目指す上で、家庭と学校が情報を共有し合うことが必要とされる場合があります。子どもの学習状況を適切に伝えることで、学校側もサポートしやすくなります。
月に1回の「学習レポート提出」が効果的
すららでは、学習の進捗状況を記録したレポートを簡単にダウンロード・提出できます。これを活用して、毎月1回程度、学校へ提出することを習慣にするのが理想です。
家庭訪問・面談にも積極的に応じる姿勢を持とう
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも前向きに応じるとよいでしょう。学校との信頼関係構築が出席扱いへの近道となります。
担任とは定期的に連絡をとって進捗共有を
メールや電話を通じて、こまめに進捗状況を共有することもポイントです。担任の先生が安心して認定に向けた書類を整えやすくなります。
注意点5・教育委員会への申請が必要なケースもある
教育委員会と連携しながら手続きを進める
一部の自治体では、出席扱いを認定するために教育委員会の承認が必要となることがあります。この場合、学校と連携して資料を整えることが不可欠です。
教育委員会用の資料については、学校側と相談しながら進めることでスムーズに申請できます。無理なく進めるためにも、早い段階で学校に相談するのがベストです。

出席扱いを成功させるには、学習の質と量、学校との信頼関係、そして教育委員会との連携もポイントだね!
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

どうすれば、すららで出席扱いをスムーズに認めてもらえるの?成功させるための具体的なポイントが知りたい!
すららを使って出席扱いを申請する際、事前準備と戦略的なアプローチが成功のカギとなります。判断基準は学校や地域によって異なるため、ここでは多くの家庭でうまくいっている成功のポイントを紹介します。
ポイント1・「前例」があることを学校に伝える
学校側が最も気にするのは「他の学校でも出席扱いされた実績があるかどうか」です。他校での成功事例を提示することで、学校の不安を和らげることができます。
すららで出席扱いになった実例を示す
「実際に他の学校で出席扱いされた」という具体的な実例は説得力があります。実績のある教材だという安心感が、学校側の承認を後押しします。
すらら公式サイトの資料を印刷して持参する
すららの公式サイトでは、出席扱いの実績や事例が掲載されています。それをプリントアウトして学校へ提示することで、前例に基づいた信頼性をアピールできます。
ポイント2・「本人のやる気」を伝える
学習意欲が高いかどうかは、出席扱いを判断する重要な材料になります。子ども自身の言葉で取り組み姿勢を伝える工夫が必要です。
学習の感想や目標を本人の言葉で書いて提出する
「すららを通じてどんな学びがあったか」「今後の目標は何か」など、本人が手書きでまとめたノートやメモを提出すると、前向きな姿勢が伝わりやすくなります。
面談には可能な限り本人も同席を
学校との面談では、本人が「頑張っている」と伝えることで、教師側の信頼感がぐっと高まります。親の言葉よりも、本人の声の方が響くことも多いのです。
ポイント3・無理のない学習計画を立てる
出席扱いは一時的な学習では認められません。継続できる現実的なスケジュールを立てることが、成功の条件です。
本人に合わせた現実的なスケジュールが成功の鍵
「1日○時間」など厳しすぎる計画では、途中で挫折してしまうリスクがあります。子どもの体調やペースを見ながら柔軟に調整することが大切です。
すららコーチに相談して学習計画を作る
すららには専任の学習サポート「すららコーチ」がいます。コーチと一緒に作成した計画は、学校への申請資料としても説得力を発揮します。
ポイント4・すららコーチを活用して証明資料を整える
すららコーチのサポートは、出席扱い申請時にも非常に役立ちます。必要書類やレポートの作成を一緒に進められるのは大きな安心材料です。
出席扱いのためのレポートや証明書を整えてもらえる
すららコーチは、進捗レポートの作成や学習証明のフォーマット作成をサポートしてくれます。学校側の要望に沿った内容で提出できるため、手続きがスムーズに進みやすくなります。

前例・意欲・計画性・サポート体制が揃えば、出席扱いの申請も成功にグッと近づくね!
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

実際にすららを使っている家庭の声はどうなんだろう?リアルな体験談を知りたい!
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

リアルな口コミは判断材料としてとても大切!メリットもデメリットも参考にしたいね。
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららって不登校の出席扱いになるの?費用やサポートのことも気になる…
すららは、不登校の子どもにとって頼れるオンライン学習教材として注目を集めていますが、「本当に出席扱いになるの?」「申請の手続きは面倒?」「料金はどれくらい?」など、気になるポイントもたくさんあるのではないでしょうか。
そこでこのセクションでは、すららを導入するにあたって多くの方が疑問に思うことをQ&A形式でご紹介していきます。不登校支援やICT学習に関する情報を交えながら、安心してすららを活用するためのヒントをお届けします。

疑問が多いところこそ、しっかり知っておくことで安心してすららを始められるね!
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに対する口コミの中には、「うざい」と感じたという意見も見られます。これは、アニメーションによる講義形式やキャラクターの声かけが一部の子どもに合わなかったことが原因とされています。学習を楽しく続けてもらうための工夫が、逆に集中を妨げると感じることもあるようです。
ただし、これはあくまで個人の好みによるものであり、実際には「わかりやすい」「楽しい」という好意的な声も多くあります。すららの学習スタイルが自分の子どもに合うかどうかは、無料体験などで一度試してみることをおすすめします。
関連ページ:すららの評判はうざい?最悪の口コミや料金、小中高向けタブレット教材の特徴を徹底分析!
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」という名称のコースは存在しませんが、無学年式で自分のペースで進められる設計や、コーチによる個別サポート体制が発達障害のあるお子さまにも適していると評価されています。
料金については通常のコースと同じく、教科数や契約期間によって異なるため、具体的な金額は公式サイトや申込ページでの確認が必要です。無理なく始められる柔軟な料金設計となっているので、まずは問い合わせや資料請求で詳細をチェックしてみてください。
関連ページ:すららの料金は発達障害の方に優遇あり?学習障害や療育手帳で安くなるかを徹底解説!
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららのタブレット学習は、一定の条件を満たせば不登校でも「出席扱い」として認められるケースがあります。これは、文部科学省が示す「ICTを活用した学習活動の出席認定」制度に準拠しているからです。
ただし、出席扱いの適用には学校や教育委員会との相談が必要となります。また、学習の進捗を記録したレポートや学習計画の提出など、正しい申請手順と実績の共有が必要です。詳細は関連ページを確認し、事前に学校に相談しておきましょう。
関連ページ:すららは不登校の出席扱いに対応?申請手順や注意点、成功のポイントを徹底解説!
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、期間限定でお得なキャンペーンコードが配布されることがあります。これにより、入会金が割引になったり、体験期間が延長されたりといった特典が受けられます。
キャンペーンコードは、すらら公式サイトや資料請求後の案内メールなどで入手可能です。使用する際は、申し込みページで該当欄にコードを入力することで自動的に適用されます。最新のキャンペーン情報は、公式のキャンペーンページをチェックしましょう。
関連ページ:すららのキャンペーンコードでお得に入会!入手方法や無料特典の詳細を紹介
すららの退会方法について教えてください
すららの退会は、すらら公式サイトのマイページからオンラインで手続きができます。ただし、解約のタイミングによっては翌月の受講料が発生する場合があるため、手続きは月末ギリギリではなく、余裕を持って行うのがおすすめです。
また、すららでは一時的な「休会制度」も用意されているため、継続が難しい場合でも解約以外の選択肢があります。詳しい手順や注意点は、公式FAQやサポート窓口で確認すると安心です。
関連ページ:すららを解約・休会するには?退会手続きの流れや期限を分かりやすく解説!
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの料金体系はとてもシンプルです。基本的には「入会金+月額の受講料」だけで学習を始めることができます。追加の教材費やシステム利用料などは発生しません。
ただし、学習に使用するタブレットやパソコンなどの端末は家庭での用意が必要です。また、希望する場合にのみ選べるオプションやサポートは、別途料金がかかる場合もありますので、契約前に公式サイトで詳細を確認しておきましょう。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららのアカウントは「1人につき1契約」が基本ルールです。つまり、兄弟での共有利用はできません。
兄弟それぞれの学習進度や記録を正しく管理するためには、個別にアカウントを契約する必要があります。ただし、事情に応じて柔軟な対応をしてもらえる場合もあるため、気になる方はすららのカスタマーサポートへ相談してみると良いでしょう。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語を含む5教科セットがあります。選べるコースとしては、
- 国語・算数・理科・社会の4教科コース
- それに英語を加えた5教科コース
英語のカリキュラムは、小学生でも理解しやすいように設計されており、アニメーションや発音練習など、楽しく学べる工夫がされています。公式サイトでは実際の教材画面も紹介されていますので、ぜひチェックしてみてください。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すらら最大の特徴の一つが「すららコーチ」による学習サポートです。専任コーチが一人ひとりに寄り添い、学習計画の作成・アドバイス・モチベーション維持をしっかりサポートしてくれます。
特に、発達障害や学習障害を抱えるお子さまには、個々の特性に合った指導と声かけが行われるため、家庭だけでの学習に不安がある保護者にも安心です。子どもが無理なく、自信を持って学べる環境が整っているのが魅力です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

「すらら」と他のタブレット学習教材って、どう違うの?不登校の子にとってはどれが一番いいのかな?
最近では、多くの家庭用タブレット教材が登場し、それぞれに独自の特徴や強みがあります。その中でも「すらら」は不登校の子どもたちへの学習支援を前提に設計されている点が大きな違いです。文部科学省が認める出席扱い制度の活用が可能で、学校に通えない期間も学びを継続しやすいのが魅力となっています。
このセクションでは、すららと他の家庭用学習教材を比較しながら、「どの教材が不登校支援に適しているのか」を見ていきます。学習スタイル、対応教科、出席扱い制度との相性など、気になるポイントを整理してご紹介します。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
|---|---|---|---|---|
| スタディサプリ 小学講座 |
2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数 理科、社会 |
✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ 小学生コース |
3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
✖ |
| オンライン 家庭教師東大先生 |
24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数 理科、社会、英語 |
✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数 理科、社会 音楽、図画工作 |
必須 |
| デキタス 小学生コース |
3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数 理科、社会 |
✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い 英単語・計算 |
必須 |
| LOGIQ LABO (ロジックラボ) |
3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師の サクシード |
12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数 理科、社会 |
✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

他の教材と比べることで、すららの強みや特長がもっとはっきり見えてきますね!
すららは不登校の出席扱いに対応?申請手順や注意点、成功のポイントを徹底解説!まとめ

結局、すららを使えば本当に出席扱いになるの?どんな準備が必要だったか覚えておきたいな。
すららは、不登校の子どもにとって大きな学びの味方です。文部科学省の「ICTを活用した学習の出席扱い制度」に対応しており、実際に多くの学校で出席扱いとして認められてきた実績があります。学習記録の提出や医師の診断書の準備、学校との連携が整えば、自宅学習でも出席と認定される可能性が高まります。
とはいえ、出席扱いの可否は学校や教育委員会の判断に委ねられるため、早い段階で担任や校長、場合によっては教育委員会とも相談しながら進めることが重要です。学習の継続性・計画性・学習内容の水準が認められるかがポイントとなります。
記事内では、出席扱いの申請手順から注意点、成功のためのコツまで詳しく解説してきました。不登校でも将来に向けて前向きに学習を続けたい方にとって、すららは強力な選択肢となるでしょう。

すららは、子どもだけでなく保護者にとっても安心できる学習環境。正しい手順と準備で出席扱いを目指しましょう!